
「七五三」は、誕生した我が子が
それまで成長したことに感謝し、
これからも健康で成長出来るようにという
願いを込めて行われる
日本独特の行事のひとつです。
現在では、女の子は三歳と七歳、
男の子は三歳と五歳に
「七五三」のお祝いが行われています。
七五三とは
古い言葉に「七歳までは神の内」という
ことわざがあります。
これは、成長環境や医療の未発達などから
七歳位までの子供の死亡率が高かったことを
指しています。

この難しい時期を無事に過ごせたお祝いとして
「七五三」の儀式が行われました。
「七五三」は、
元は平安時代頃に宮中で行われていた
「髪置」「袴着」「帯解き」という3つの儀式が
その始まりだとされています。
成長の節目となる3歳、5歳、7歳になると順に
「髪置」「袴着」「帯解き」を行って、
無事に育ったことを神様に感謝し、
その後の長寿を祈願する儀式を行ったと
いうのがその背景です。
この儀式は鎌倉時代にも引き継がれ、
江戸時代には武家や商人の間にも広まりました。
明治時代に入ると庶民にも広まり、
「七五三」が現在の形に落ち着いたのは
大正時代の頃だとされています。

三歳「髪置きの儀」
平安時代には、男女ともに生後七日で
産毛を剃って坊主頭にし、
丸坊主のまま3歳の春まで育てるという
風習がありました。
これは坊主にして頭を清潔に保つことが
命を脅かす感染症から子供を守るためと
されていました。

そして三歳の春を迎える頃に
「髪置きの儀」を行って成長を祝い、
髪の毛を伸ばし始めました。

「髪置きの儀」では、絹糸や真綿で
かつら(綿白髪)を作ってこれを頭に被せます。これは白髪になるまで長生きするようにという
我が子の健康を祈る親の一途な願いが
込められています。
この年齢では、まだ帯を結びませんので、
着物に付いている「付け帯」(つけおび)
という紐を結んで着物を着付けます。
女の子はその上に「被布」(ひふ)と呼ばれる
上着を着用して、正装とします。
男の子は「兵児帯」(へこおび)と
「袖なし羽織(陣羽織)」を着せることが
多いようです。
五歳「袴着(はかまぎ)の儀」
平安時代、五~七歳の頃に
当時の正装である袴を初めて身に付ける
「袴着の儀」を執り行ない、
この儀式を経て男の子は少年の仲間入りをし、
羽織袴を身に付けたとされています。
当初は男女ともに行っていた儀式でしたが、
江戸時代に男の子のみの儀式に
変わっていきました。

儀式はまず天下取りの意味を持つ
碁盤の上に立って吉方に向き、
縁起が良いとされる左足から袴を履きました。
また冠を被って
四方の神を拝んだとも言われており、
四方の敵に勝つという願いが込められています。

現代の皇室でも、男児の儀式として
数え五歳の時に「着袴の儀」、
その後に碁盤の上から飛び降りる
「深曽木(ふかそぎ)の儀」が続けられています。
この「深曽木(ふかそぎ)の儀」に倣い、
碁盤の上から飛び降りる「碁盤の儀」を
七五三詣の時期に開催している神社が
全国各地にあります。
五歳の男児が袴を着用する年齢になります。
着物に「角帯」(かくおび)を締めて、
その上に「袴」を着用し、
そして五歳のお祝い着のメインでもある
「羽織」を着用します。
羽織は兜や鷹、虎などの勇猛な姿を描いた
「絵羽」(えば)のものも多く、
男の子の逞しい成長への祈りを象徴する
アイテムです。
七歳「帯解(おびとき)の儀」

鎌倉時代になると、
子供が大人の着物を着て
初めて帯を締める儀式が始まりました。
着物の付け紐を取り、
大人と同じ本裁ちの着物を
着るようになったことを祝う儀式です。

これが室町時代になると
「帯解きの儀」として制定されました。
当初は男女ともに
九歳になった頃に行われていました。
江戸時代になり五歳の「袴着の儀」が
男児だけの儀式として定着するようになると、
この「帯解きの儀」は、
女児が七歳に行う儀式として
以後執り行われるようになりました。
この「帯解きの儀」を経て
大人の女性へ歩み始めると認められていました。

三歳・五歳・七歳を節目とした理由は、
暦がChinaから伝わった際に、
奇数は「陽」、
つまり縁起が良いとされたからだとか、
「三歳で言葉を理解し、五歳で知恵がつき、
七歳で乳歯が生え変わる」という
成長の節目の歳だからなどと言われています。
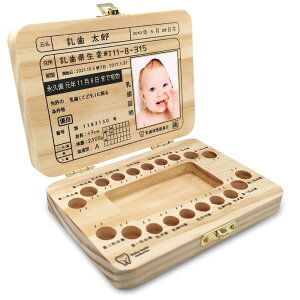
中でも七歳は、「神のうち」から「人間」として
現世に完全に誕生する
大きな祝いの歳とされていたため、
「七五三」の中でも七歳の儀式を重視する
地方が多かったようです。
七歳は、それまで用いていた「付け帯」を取り去り、帯を締める年齢になります。
まだ、「肩揚げ」こそしてありますが、
「腰紐」を用いて着物を着付け、帯を結ぶという大人と同様の着方になります。
そして「しごき」という飾り帯で帯周りを飾ります。
更に女性の身だしなみである
「筥迫(箱迫)」(はこせこ)を懐中し、
立派なレディーになります。
千歳飴(ちとせあめ)
子供の成長を願って、長寿の意味の
千年という名前が付いた「千歳飴」。
その名の通り、「千歳まで生きる」ことを
願っての縁起物です。
千歳飴の形
精製した白砂糖を練り固めて作った
「太白飴」(たいはくあめ)を細長くし、
紅白それぞれの色で染めて作られています。
この長い飴を食べることで
「細く長く」、そして「粘り強く」
いつまでも元気で健やかに成長しますようにと
祈願する意味があります。
因みに「千歳飴」の大きさは、
直径1.5㎝・長さ1m以内と決まっているそうです。

細長い形で、1本丸ごとは食べにくいですが、
「長さに意味があるので
食べる時に折ってはいけない」
と言われています。

縁起物なので、食べやすく切って
近所におすそ分けした方が良いとする地方も
あるようです。
また、「お福分け」として「七五三」の内祝に
千歳飴を贈る地方もあります。
千歳飴の起源
この「千歳飴」が七五三に配られるように
なったのは江戸時代のようです。
起源については諸説あります。
飴の生地を長く伸ばして作るので、
「千年、長生き出来る」という
宣伝文句で販売し、
大ヒットしたと言われています。
昔は幼いうちに亡くなる子供が多かったので、
元気に成長して長生きしてくれることを願い、
七五三のお祝いの定番になりました。
大坂の飴売りが江戸に出て売り始めたとする説
元和元(1615)年に、大坂の平野甚左衛門が
飴の販路を拡大するために江戸に出て、
浅草寺の境内で飴を売り始めたのが
始まりというものです。
当時は、千歳飴は「せんざいあめ」と読まれ、
その飴を食べれば千歳まで生きられるとして
人気を集めました。
浅草の七兵衛を発祥とする説
元禄・宝永年間(1704〜1711年)に、
江戸・浅草の七兵衛(しちびょうえ)という飴売りが、
紅白の飴を「千年飴」として売り出したと
いうものです。
千年という言葉が長寿をイメージさせる
縁起の良いものであったため、
話題になりました。
文政8(1825)年刊の柳亭種彦(りゅうていたねひこ)の
『還魂紙料』(かんこうしりょう)には、
「千年飴」(せんねんあめ)として、
次のように書かれています。
元禄宝永の比(ころ)、
江戸浅草に七兵衛といふ飴売あり。
その飴の名を千年飴、また寿命糖(じゅみょうとう)ともいふ。
今俗(いまぞく)に長袋(ながぶくろ)といふ飴に
千歳飴(せんざいあめ)と書(かく)こと、
彼(かの)七兵衛に起(おこ)れり。
神田明神を発祥とする説
神田明神の社頭で売られていた
「祝い飴」が発祥だというものです。
神田明神では、今も昔と変わらず、
「七五三」のお参りに来た子供達に
千歳飴が授与されています。







